「東洋医学に分類される漢方医学は、中医学の考えをもとに日本独自で発展した分野です。そして、漢方薬は、ショウガやシナモンなど、身体に与える効能や効果を指す“食効(しょっこう)”を持つ食材を用いて調合されています」と話すのは、漢方医学・自然医学に基づいた診療を行う『イシハラクリニック』副院長の石原新菜先生です。
漢方薬は更年期症状をはじめとした、女性の健康課題に有用だとされています。その理由を教えていただきながら、更年期世代が症状に合わせて取り入れたい漢方薬についても伺いました。
漢方医学と西洋医学、それぞれの特性
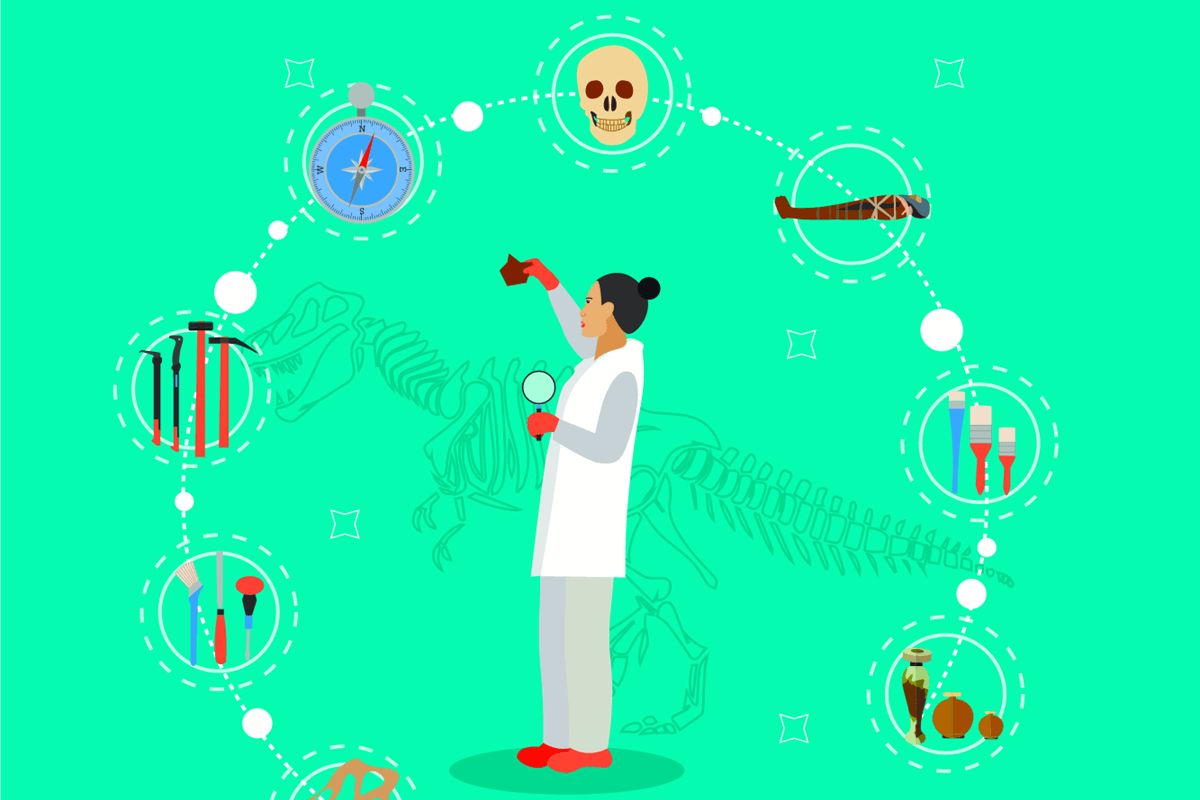
「更年期世代の心身のゆらぎは、女性ホルモンの急激な変化に伴い、自律神経が乱れることが大きな要因となっています。漢方医学は、このゆらぎに寄り添って調える力があることから、更年期の症状ケアとの相性がいいとされています。
病院で行われる治療は、基本的には西洋医学に基づいています。更年期症状の場合、不足している女性ホルモンを補うホルモン補充療法など、ダイレクトな治療を行うのが西洋医学の特徴です。
一方、漢方医学は、なぜその症状が現れているのかを多角的な視点で考えます。そして、気・血・水(きけつすい)の考えのもと、身体全体のバランスを整えることを重視しています。気はエネルギー源、血は血液や栄養、水は血液以外の体液を指しています。お互いに影響し合っている関係なので、どれかひとつのバランスが崩れると他の要素にも影響が出るという考え方です。
西洋医学、漢方医学、どちらかがいいということではなく、得意分野が異なります。それぞれの特性を知ったうえで、どちらかを選択することもできますし、組み合わせることも可能です」(石原新菜先生・以下同)
体質や生活習慣など、包括的に治療
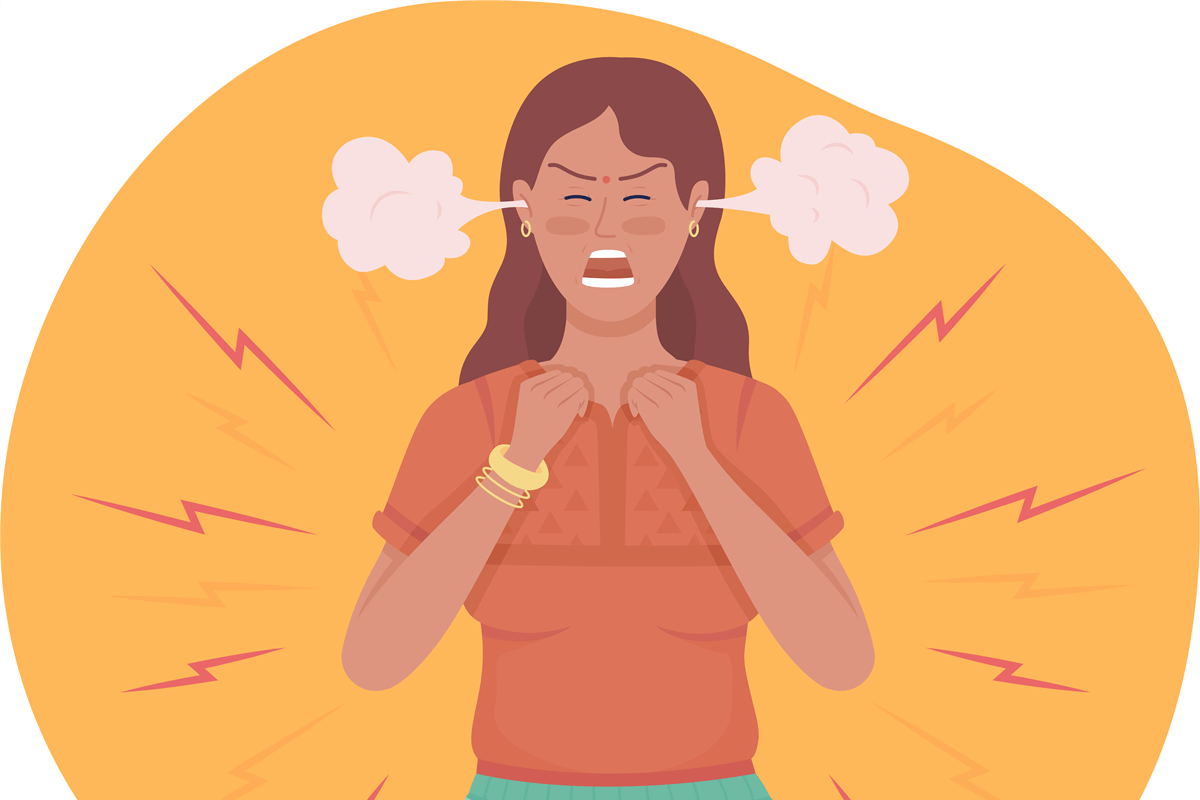
「ホットフラッシュやのぼせなどは自律神経の症状、イライラや不安感などはメンタルヘルスの症状、冷えやむくみ、肩こりなどの身体的な症状と、更年期症状は多岐に渡ります。漢方医学では、それらをまとめてバランスを見ながらゆるやかに整えていくイメージです。そのため、気になる症状をピンポイントで治療するのではなく、包括的に診ていきます。
そのうえで、症状を理解し、体質や生活習慣、仕事環境なども考慮して漢方薬を処方していきます」
更年期世代が知っておきたい漢方薬6選

1. 体力がなく、身体的な症状が出やすい【当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)】
「疲れやすい、むくみやすい、冷えている、肩こりがひどいなど、身体的な症状が出やすい人に向いています。血と水の巡りを改善して、基礎体力を底上げしていきます。
当帰芍薬散は、更年期症状にかぎらず、生理にまつわる不調や不妊症においても処方されることが多いです」
2. 心と身体の両方からゆらぐ【加味逍遥散(かみしょうようさん)】
「イライラ、不安感、気分の落ち込みなどのメンタルヘルスの症状と、ホットフラッシュや肩こりといった身体的な症状がある場合は、気の流れを整えて、血の巡りをすることでやわらいでいきます。
加味逍遙散は心身両方に働きかけてくれることから、更年期症状を代表する処方です」
3. 冷えなど血の滞りからくる症状【桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)】
「冷えているのに、顔はほてりやすいなど、冷えと熱さの同居しているタイプは、血の流れを改善していくことが大切です。
桂枝茯苓丸は、ホットフラッシュの症状をやわらげ、頭や顔ののぼせ、赤ら顔にも効果が期待できます」
4.不眠症状が気になる【酸棗仁湯(さんそうにんとう)】
「エストロゲンの低下は自律神経に影響していることから、睡眠の質が落ちやすく、不眠になるケースもあります。
酸棗仁湯は、神経の高ぶりを鎮めて自然な眠りへ導く働きがあり、漢方薬の安眠処方です」
5.呼吸の浅さ、のどの違和感【半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)】
「自律神経の乱れから、不安や緊張感がのどや胸に現れ、のどに違和感がある、呼吸が浅くなった気がするといった症状を感じる場合もあります。気が停滞している可能性がありますので、半夏厚朴湯で流れをスムーズにしていきます」
6. 排尿トラブルや骨・関節が気になる【八味地黄丸(はちみじおうがん)】
「漢方医学では、腎はエネルギーの源であり、ホルモンバランスとも関係しています。更年期は腎の力が衰える時期でもあり、それが頻尿などの排尿トラブルや指の関節が痛いなどの骨・関節の症状として現れることがあります。
八味地黄丸は、腎を補って身体全体の衰えをゆるやかに整える漢方薬です」
生活習慣の見直しも重要
「漢方薬は、体質や症状にあったものを選ぶことが重要になります。ドラッグストアでも購入可能ですが、初めて取り入れる場合は特に、専門医の診断のうえ処方してもらうほうがより安心できると思います。そして、効果実感はゆるやかですので、1~3ヶ月は継続して様子を見ていきましょう。
ただし、漢方薬を服用しているからOKではありません。漢方薬はサポート役と捉えて、これまでの生活習慣を見直してアップデートしながら、総合的に整えていくことを重視してください」
執筆/木川誠子
No.00193
2025年11月21日リリース
