がんの診断を受けた時、多くの人が感じるのは「治療できるのか」という不安。そこには、「治療費はどれくらいかかるのだろう」という現実的な悩みも含まれているのではないでしょうか。
標準治療と呼ばれる保険診療内であっても、通院・入院・手術・薬代と費用は積み重なります。さらには、生活費も関係してきます。ですが、その不安や悩みは制度や保険の仕組みを知り、準備しておくことで解消されることがあると考えます。
そこで、実際にがん治療を経験した4人の声を通じて、治療とお金は切り離せない現実と、備えの大切さを見ていきます。
Aさんの体験談:民間保険の落とし穴と見直しの学び
Aさんは、乳がんの治療を通して「保険は内容を確認し、定期的に見直すことが大切だと実感しました」と話します。
「過去には、【入院が一定日数を超えないと給付対象外になる】という制限に直面したことがありましたが、その経験が学びとなり、現在は自分に合った契約を選び直すことができました。
また、放射線治療では【線量や回数が条件になる場合がある】と看護師からアドバイスを受け、実際に保険約款を確認したこともあり、治療のことだけでなく、保険制度や契約内容を理解しておくことの重要性を痛感しました。
知識を持つことで不安が減り、安心して治療に臨めたことが大きな収穫です」
Aさんは、こうした経験から「保険は加入して終わりではなく、医療の進歩や自分のライフステージに合わせて見直していくもの」だと前向きに捉えるようになったそうです。
Bさんの体験談:高額療養費に支えられた日々
52歳で乳がんの診断を受けたBさんは、手術・放射線治療の過程で【高額療養費制度】に助けられたひとりです。
「入院や手術で大きな額の請求を覚悟していましたが、上限額を超えた分は払い戻され、心理的な負担が軽くなりました。
加えて、加入していた民間のがん保険からの一時金が生活費の橋渡しとなり、食費や日用品に充てられたことが治療継続の安心につながりました」
Cさんの体験談:早期発見の重要性を再認識
34歳で子宮頸がんの前がん病変(異形成)を指摘されたCさんは、「定期検診のおかげで早期に発見されたことが大きかったです」と話します
「費用は1年4か月で6~7万円です。大きな負担ではありませんでしたが、【定期検診での早期発見】がなければ、手術や治療費は何倍にも膨らんだと思います。
がんになる前に見つかったのは本当に幸運。毎年検診を受けていた自分を褒めたいです」
そう語る彼女の言葉には、備えの大切さが凝縮されています。
Dさんの体験談:民間の三大疾病保険に救われた
ステージ2Aの乳がん治療後、脳転移を経験したDさんは、民間の保険と公的制度に助けられたと話します。
「最初の乳がん時は、加入していた民間の三大疾病保険に助けられました。ですが、その詩兄一時金を受け取っていたため、脳転移の時には受け取れず、入院費は貯金を取り崩すしかありませんでした。
それでも、健康保険に加入している人が高額な医療費の支払いを抑えるために利用できる制度の【限度額認定証】の自己負担軽減には救われました。この公的制度を知らずにいたら、生活はもっと追い詰められていただろうと思います」
公的制度と民間保険の両輪

がん治療の経験者の声から浮かび上がったのは、【公的制度と民間保険の両輪】が大きな支えになっていたという点です。
高額療養費制度などの公的サポートは誰もが利用できる仕組みであり、治療費の急な負担を軽減します。一方で民間保険は、一時金や給付によって生活費や心理的な余裕を生み出し、不安を和らげてくれます。
ただし、公的制度の健康保険と一般企業のサービスである医療保険は混同しがちです。それぞれ役割が異なりますので、両方の仕組みを整理することも大切です。
―治療に役立つ制度のミニガイド―
●公的医療保険の基本
会社員が入る社会保険、自営業者・フリーランスが加入する国民健康保険などの公的な健康保険は、治療費が3割負担になるのが原則です。
●高額療養費制度
【限度額適用認定証】を事前発行すれば、窓口での支払いを上限までに抑えられます。マイナ保険証での簡略化にも対応が広がっています。
●自治体の支援
ウィッグや補整具の助成などがありますが、内容や上限、申請方法は各自治体で異なるため、居住地の福祉窓口で確認をしておくと安心です。
民間保険の役割は?
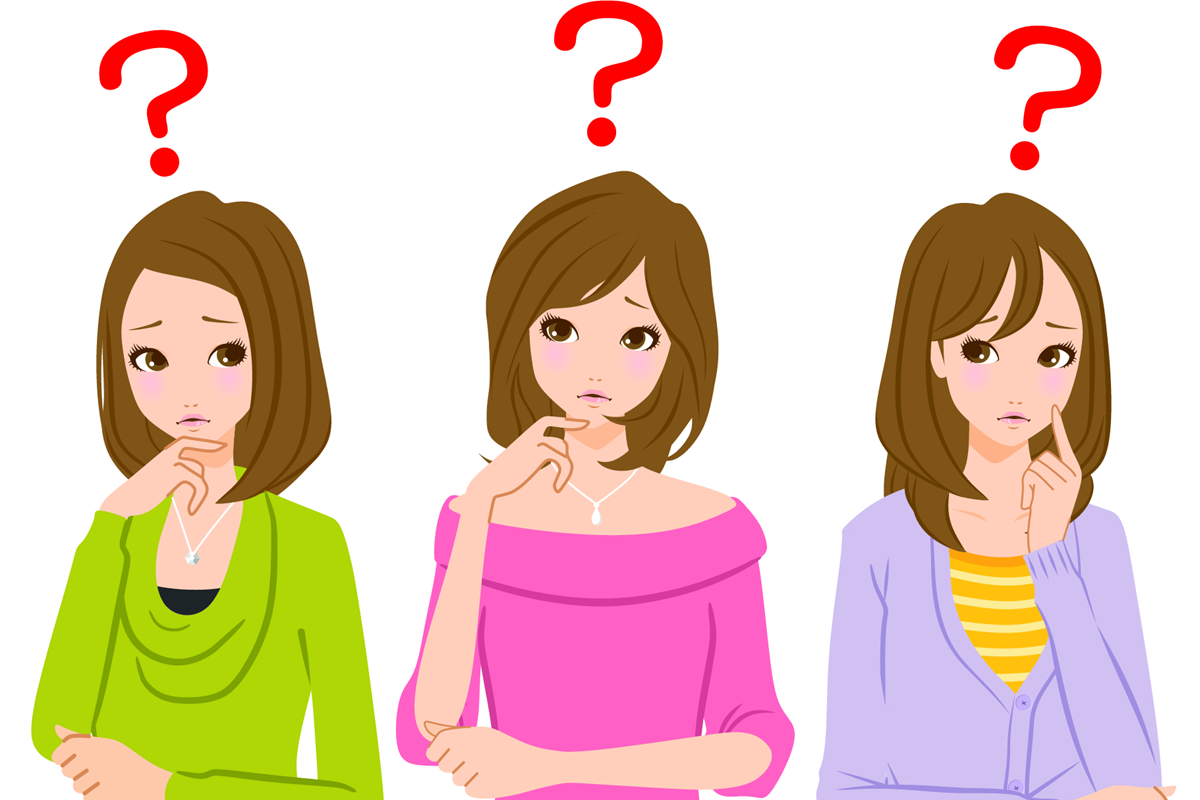
公的医療制度だけでも、治療を受けられる土台は整っています。けれど、がんサバイバーから、「民間保険からの一時金で生活費の補填ができた」「高額療養費制度とあわせて給付を受けられたことで、治療の選択に迷いがなくなり、気持ちが前向きになれた」という声もあります。
なかには、短期入院や外来中心などの治療スタイルに契約が対応していない、放射線治療の線量や回数で支給条件が異なる場合があります。だからこそ、「今の治療に合った内容かどうかを定期的に見直す必要がある」というが声も。
民間保険は必須ではありませんが、安心を重ねるためのオプションとして機能すると考えられます。いざという時、生活や心の余裕を広げたい人にとって、民間保険は選択肢のひとつとなるのではないでしょうか。公的制度を理解したうえで、ライフスタイルにあった“安心の形”を考えてみてください。
検診も制度もあなたの味方
 がんサバイバーの声からも分かるように、がん治療にはお金の不安がつきまといます。高額療養費制度や民間保険といった仕組みを知り、備えておくことは、治療を続けるための安心につながります。
がんサバイバーの声からも分かるように、がん治療にはお金の不安がつきまといます。高額療養費制度や民間保険といった仕組みを知り、備えておくことは、治療を続けるための安心につながります。
公的制度や民間保険による治療中の安心と、検診による早期発見の安心はどちらも欠かせません。両方を意識することが本当の備えといえます。
執筆/今泉まいこ
No.00188
2025年10月17日リリース
