近年、ウィメンズヘルスやセクシャルウェルネスについて語られる機会が増えてきました。そして、家庭内での性教育の重要性も広まってきています。そんな中で、「女性器(腟)をどういった言葉で伝えるのがいいのだろう?」「直接的な表現でも問題ないのかな?」と、思ったことはありませんか?
そこで今回は、30年以上に渡り性教育に携わる、東海大学教授 小貫大輔先生に女性器の呼び方の変遷(へんせん)や家庭で性教育をする際に大事にしたいことなどについてお伺いしました。
※この記事内での女性器は腟を指します。
多くの家庭では女性器の呼び名がない
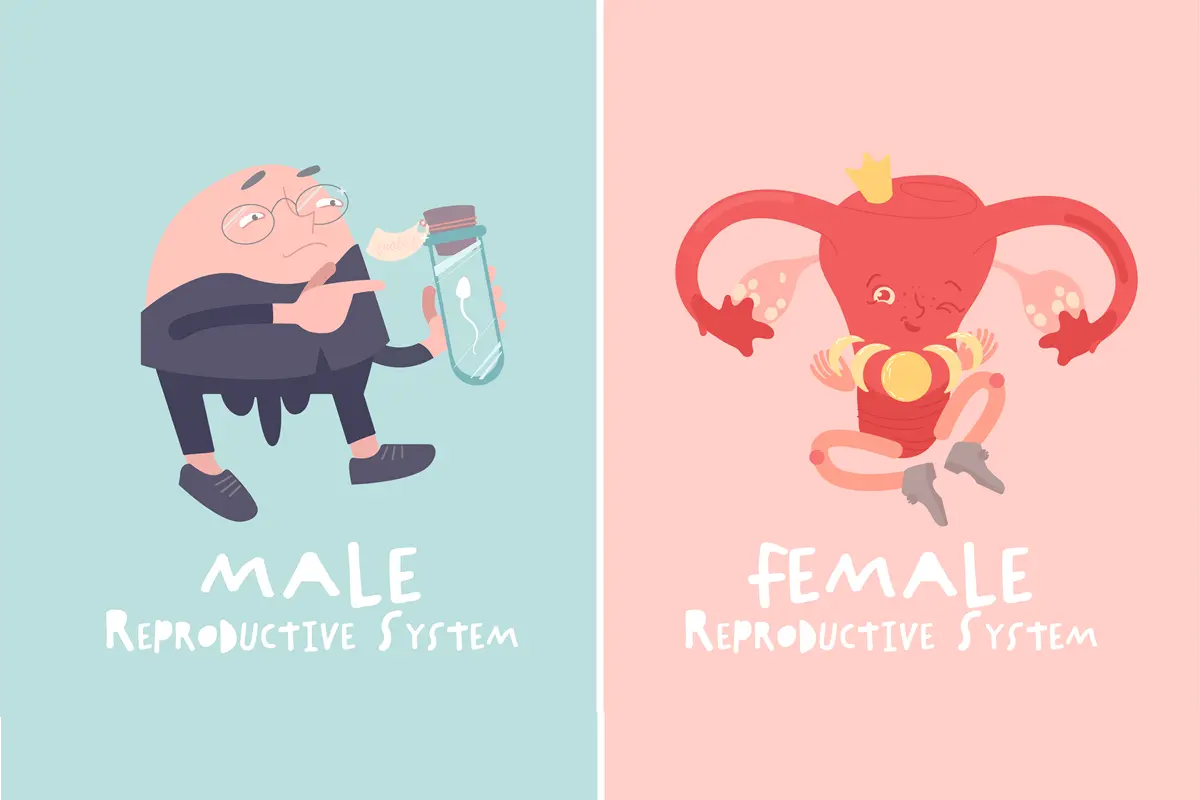
「以前、NHKが展開する『シチズンラボ 生理リサーチ』(※)というプロジェクトに参加し、視聴者にアンケートを実施しました。その中で『赤ちゃんが生まれてくる通り道のことを誰に教わりましたか?』と質問したところ、約半数の48%が学校や保健室の先生と回答。家庭で教わったと答えた人はわずか12%でした。さらに、家庭内で女性器に特定の呼び名があったかどうかについては、多くの人がなかったと答えています。
日本の多くの家庭では女性器の呼び名がないのが現状。ですが、海外では子ども向けのかわいらしい呼び名が存在します。性器の衛生やプライバシーについて、家庭内で会話をする必要があるからですが、正式名称であるVagina(ヴァギナ)に自然と紐づいていくというメリットもあるでしょう。
日本では、かつて【おまんこ】【おめこ】といった呼び名がありました。言葉自体に悪い意味はないものの、現在では公に言ってはいけないと、強いタブー意識が伴うようになりました。このことを踏まえると、その国の文化や社会の風潮も、女性器の呼び名に影響を与えていると考えられます」(小貫先生・以下同)
構造も呼び方に関係している
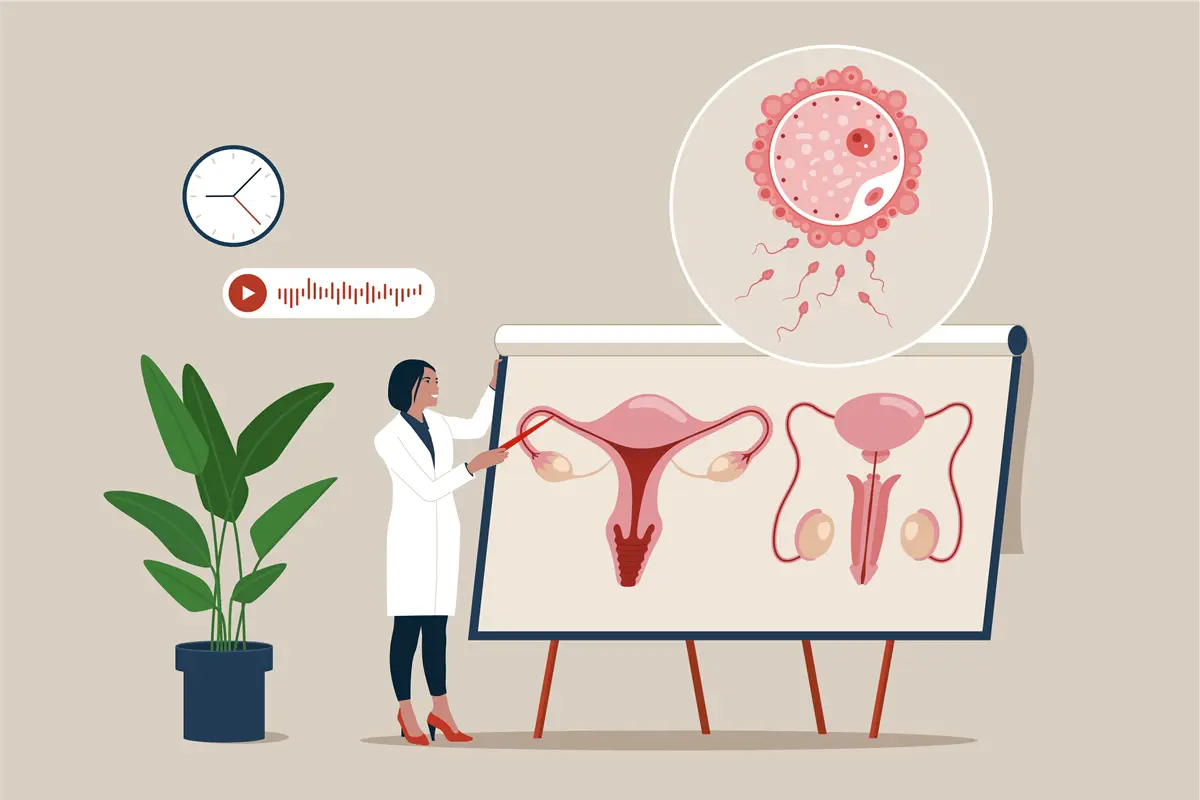
「男性器の場合、【おちんちん】という呼び名があり、時代を越えて広く使われている一方で、女性器には共通の呼び名が存在しません。
過去には、日本の性教育の先駆者と呼ばれる北沢杏子さんがやなせたかしさんと制作した絵本『なぜなの ママ?』(復刊ドットコム)の中で【われめさん】という呼び名を提案したことがありました。ですが、すぐに性的な意味に結び付けられてしまい、広く普及するに至りませんでした。ほかにも、【あそこ】や【下】などの表現が使われることもありますが、これらも直接的な言葉を避けたいという気持ちから生まれた呼び方だと想像ができます。
女性器の共通の呼び名が存在していないのには、構造的な特徴も関係していると考えられます。男性器は身体の外に出ているため、目で見ることも、触ることも容易です。子どもの時から性器に触れたり、引っ張ったりするのが当たり前で、そもそもそうしなければおしっこもできません。
一方、女性器は外からは見えにくく、構造も複雑。鏡を使わなければ見ることができませんし、触ることも意識的に行う必要があります。成人しても自分の性器を見たことがない女性は多いように思いますが、構造的な特徴が影響していると考えます。そこに心理的なハードルやタブー視する風潮が相互に働くことで、女性器についてオープンに語ることをより難しくしているように思います」
“おまた”がよく使われるように
「女性器の呼び名が定着していないなかではありますが、ここ10年ほどは【おまた】という呼び名が次第に使われるようになってきました。その表現を初めて聞いた時、私自身はあいまいな婉曲表現(えんきょくひょうげん)だと感じたのを覚えています。男性にも股はあるうえ、腟口だけでなく外陰部やクリトリスなども含めた広い領域を指していてわかりにくいと思ったのです。
しかし、最近ではNHKの番組でも使用されるほど広く浸透してきており、それはいいことだと思います。小さな子どもにも伝えやすく、公の場でも使いやすい呼び名が生まれてきたことをポジティブに捉えています」
家庭の中で呼び名があることは重要

「家庭内で女性器の呼び名があることは、子どもへの性教育においてとても重要です。子どもが生まれた時などのタイミングで、性教育の方針や女性器・男性器の呼び名について、事前に家庭内で話し合っておくといいでしょう。
例えば、近年用いられている【おまた】という呼び名を家庭の中でも使用することによって、子どもは性器の存在をより理解しやすくなります。そして、その家庭での呼び名は、子どもの成長に応じて正式な呼び名につなげていくのが望ましいです。【お母さんのおまたには、赤ちゃんが生まれてくる時の通り道の出口があるんだよ。その通る道のことを腟って言うんだよ】といったように説明をすることで、正しい知識へと導くことができます」
そして、「恥ずかしがらず、話をすることも大事です」と、小貫先生は教えてくれました。親が恥ずかしがってしまうと、子どもは「女性器の話は恥ずかしいことなんだ」と感じてしまうから。子どもに教えることをきっかけに、親自身が性について勉強してみてはどうでしょうか。性への苦手意識を乗り越えることにもつながると思います。
執筆/平野絵梨香
No.00184
2025年9月12日リリース
