2024年10月に『国立研究開発法人 国立成育医療研究センター』に、女性の健康総合センターが設立されました。女性の健康・疾患に特化した研究の推進、女性の健康に関する最新のエビデンス収集や情報提供を行う役割を担います。国の機関として誕生したとあって、女性の健康に関する取り組みの活性化が期待されています。
今回は、女性の健康総合センター長である小宮ひろみさんにインタビューし、女性の健康総合センターの役割、目指す未来などを伺いました。
身体・心理・社会の3つの視点からアプローチ
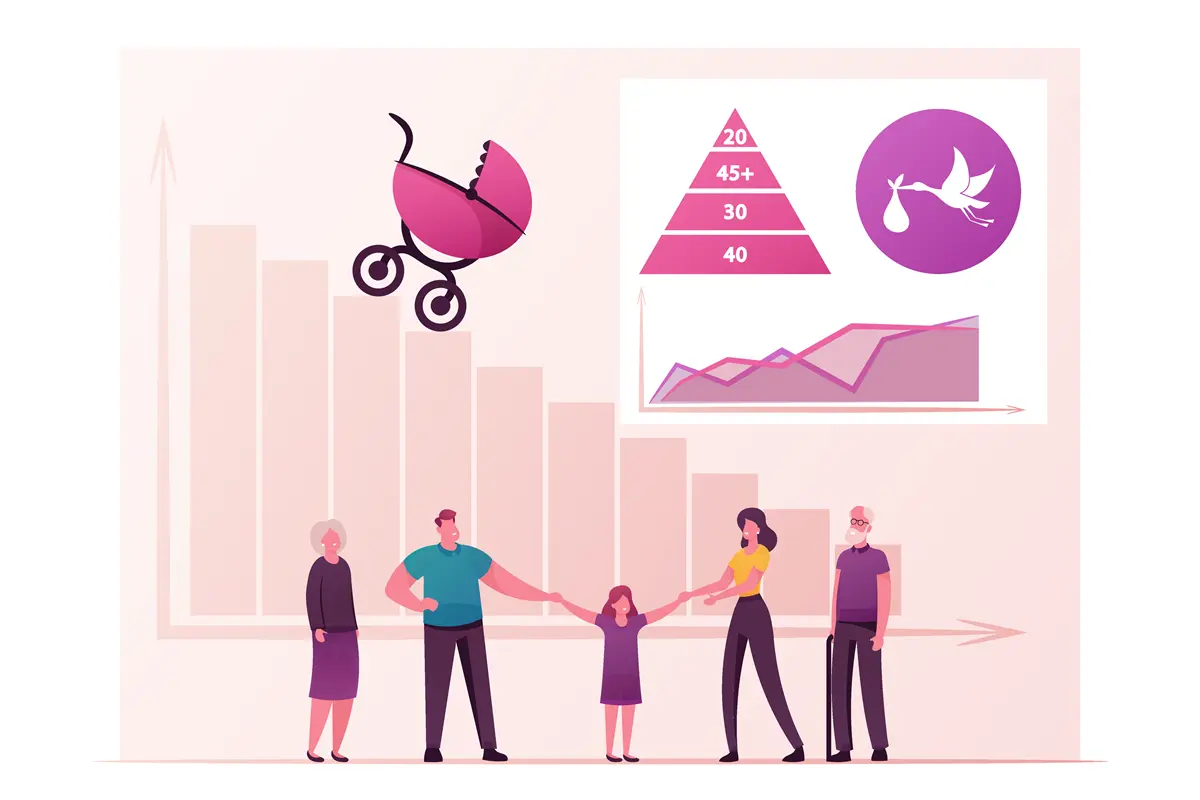
「女性の健康総合センターは、ライフステージと性差に着目して女性の健康を推進していくことを目的にしています。女性の健康視点では、思春期、性成熟期、更年期、老年期のそれぞれのライフステージでエストロゲンなどのホルモン分泌は変化しますし、社会や環境因子の影響を受けやすいです。
フィジカルの問題である【身体】、心の問題である【心理】、そして、【社会】の3つの側面から捉えて、理解をしていくバイオ・サイコ・ソーシャルの考えで、女性の健康に向き合い、ウェルビーイングを目指していきます」(小宮ひろみさん・以下同)
女性の健康総合センターの5つの取り組み

1.女性の健康データを構築していく
「女性の健康に関するデータは増えてきているものの、一括管理が行われておらず、活用するのが難しい状況にあると考えています。そこで、データ収集と管理、さらには解析なども行います。
そして、窓口も設置して、データを提供できる体制も整えます。女性の健康総合センターに問い合わせると、知りたい、活用したい女性の健康データが得られると思っていただけるように構築していきます」
2.多角的な視点での基礎・臨床研究からの社会実装へ
「女性の健康課題は多岐に渡ることから、医学的な視点のみならず、社会学なども取り入れながら、多角的なアプローチで研究を進めます。
さらに、その研究成果は社会実装化を目指します。そのために、オープンイノベーションセンターを設立し、さまざまな研究機関、民間企業、スタートアップなどと協働し、アイデアや技術を取り入れていきながら、イノベーションを生み出していきます」
3.エビデンスの活用と人材育成
「女性の健康にはエビデンスが重要であるため、広く発信していくこと。さらには、そのエビデンスを活かしながら、教育プログラムやコンテンツの開発を行い、人材育成にも力を入れていきます」
4.プレコンセプションケアの浸透
「妊娠を希望するしないに関わらず、将来のライフプランを考えて日々の生活や健康と向き合うことで、将来の自分の健康につなげていく【プレコンセプションケア】は重要だと考え、相談・健診・カウンセリングの実施や全国に浸透させていくための取り組みも行います」
5.女性に特化した診療センターを設置
「成育医療研究センターの病院内に、女性に対して幅広い診療を提供する『女性総合診療センター』を立ち上げます。
女性内科、女性外科/婦人科、不妊診療科、女性精神科、女性歯科の5つの診療科で構成し、各科が連携しながら女性に対して総合的な診療を提供します」
個別化医療を目指していく

「女性の健康総合センターは、女性医療に加えて、性差医療にも力を入れています。
性差を形成する要因として、性染色体、性ホルモン、内外性器や社会・文化的要因(ジェンダー)があると考えています。これまでは性差を考慮した医学・医療はほとんどなされておらず、男性から得られた研究内容が女性にも当てはめられていたところがあります。男性のデータに比べると女性のデータが少ない現状があるため、女性の健康データの構築を推進しながらも、すべての細胞には性染色体(XX=男性、XY=女性)があることも考慮していく必要があります。
遺伝子、性ホルモン、ジェンダーの性差に着目した研究を進めていくことで、新たな診断、治療法、予防法などの開発に貢献しながら、性別に関わらずすべての人の健康推進。そして、女性医療、性差医療の先には個別化医療を見据えています。
また、医療関係者やフェムケアメーカーなどの企業のみならず、すべての人に情報を届けていくことも意識しています。具体的には、誰もが参加できる形で女性の健康にまつわるセミナーの実施やイベントの開催を計画しています。
女性の健康総合センターからの情報が正しいソースとして認識され、女性はもちろんのこと、性別にかかわらず、みんなが健康になったね、となる未来を目指して取り組んでいきます」
女性の健康総合センター
〒157-8535
東京都世田谷区大蔵2-10-1
最新情報はこちらから→https://x.com/ncchd_pr
No.00166
2025年4月24日リリース
