『ジャパン・セックス・サーベイ2024(※)』の調査結果によると、取り入れている避妊法としてもっとも多いのはコンドームで約60%。次いで、外出しと言われる腟外射精が約20%となっています。どちらも男性主体の方法で、腟外射精にいたっては避妊をしているとはいいがたいです。
一方、女性主体の避妊法であるピルは4.3%と、前回の2020年調査よりは1.6%増加しているものの、まだまだ周知されていない印象があります。
「予期しない妊娠へのリスクを下げる目的や女性の自己決定権を守るうえでも、女性主体の避妊法を知っておくことは大切です」と話すのは、リプロダクティブヘルス・ライツ(SHSR)の発信も積極的に行う乳腺放射線科医・医学博士 フォックス岡本聡子先生。その重要性と女性主体の避妊法の種類について教えていただきます。
【リプロダクティブヘルス・ライツを知っておこう】
主な女性主体の避妊法

●ピル(経口避妊薬)
もっとも一般的なのは、ピルです。エストロゲンとプロゲスチン(黄体ホルモン)を含み、排卵を抑制する低用量タイプ、ホルモン量がより少なく、副作用のリスクが低い超低用量タイプなど、いくつか種類があります。毎日服用する必要がありますが、生理のコントロールも可能になり、取り入れやすい方法です。
●子宮内避妊具
子宮内に装着するタイプです。例えば、ミレーナの場合は、子宮内でプロゲスチンを放出して、子宮内膜を薄くすることで避妊につながります。一度、装着すると約5年間は有効とされています。
●ホルモン避妊パッチ
皮膚に貼るタイプの避妊方法です。ピルと同じようなメカニズムで避妊が行え、1週間ごとに張り替えていきます。ピルの飲み忘れを心配する場合は、パッチタイプがおすすめです。
「近年は特に、ピルのオンライン処方サービスが発展し、より身近な選択肢になっていると思います。健康状態やライフスタイルに合わせて選ぶことが可能ですので、医師と相談しながら自分に合う方法を取り入れてみてください。コンドームと併用して取り入れることで、より避妊率を高めることができます。
また、避妊に失敗した時などの緊急時に、性行為から72時間以内に服用することで妊娠を避けることができる緊急避妊薬(アフターピル)の存在も知っておくとより安心です。日本では処方箋が必要ではありますが、アフターピルへのアクセスを確保しておくことも、女性主体の避妊法を選択できる環境作りになります」(フォックス岡本聡子先生・以下同)
【ピルは避妊、生理コントロール、病気の予防につながる薬。ピルの役割をきちんと知る 】
心身の健康を守ることにつながる
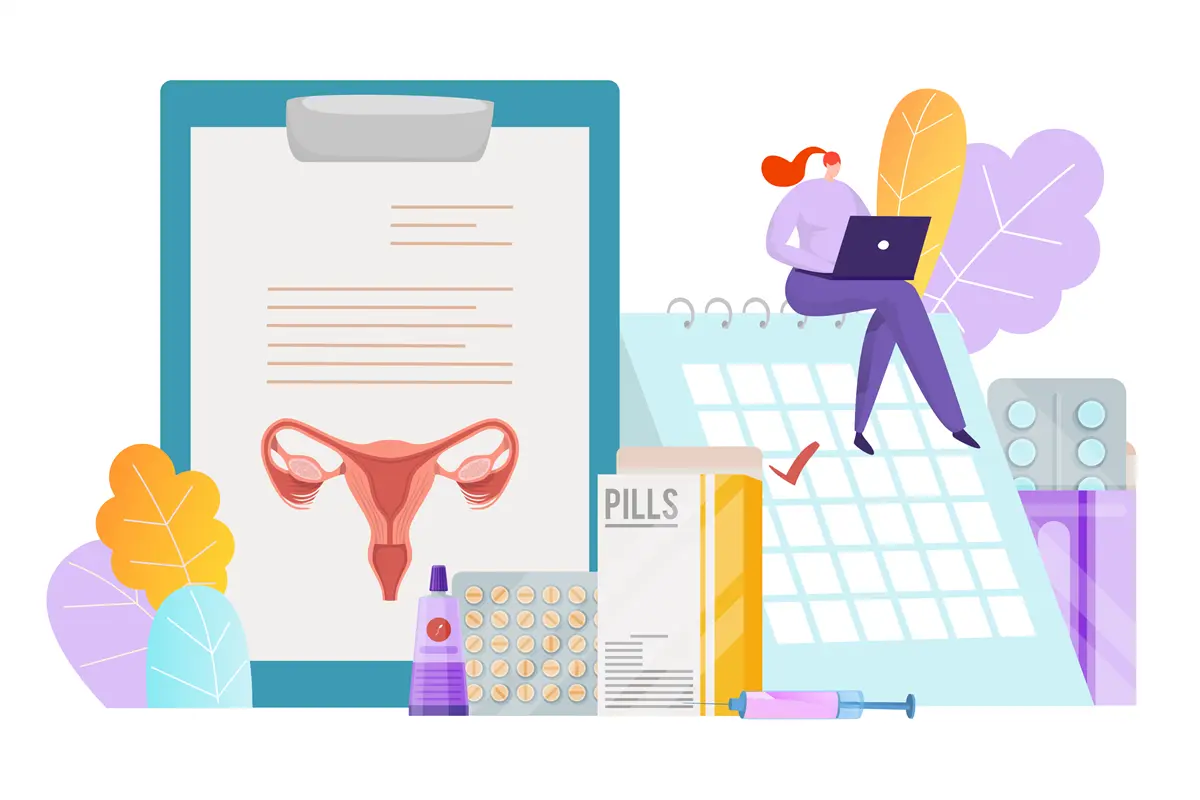
「避妊の選択肢が増えることは、心身の健康を守ること。そして、ライフプランの幅を広げることにつながります。そのため、女性主体の避妊法は、女性が自らの身体と人生の選択をコントロール・決定するための手段といえます」
●予期しない妊娠のリスクの減少
「予期しない、望まない妊娠は、心身の負担のみならず、経済的負担も大きく、ライフプランにも影響してきます。そういった視点からも避妊について考えること、行動することはとても重要です」
●自己決定権を守る
「避妊は、妊娠を防ぐための手段だけではなく、自分の身体の選択をする権利の一部でもあります。
例えば、コンドームの場合、相手の協力が必要になりますが、女性主体の避妊法は自分自身で選択したうえで避妊ができることが大きな利点です」
●経済的な自立を支える
「女性が自ら避妊を行なうことは、予期しない妊娠で学びやキャリアの中断を防ぐことにつながります。教育を受ける機会の確保やキャリアの選択ができることは、将来の経済的な自立を支えるためにも必要なこと。
より整った環境で、経済的に安定してから妊娠・出産を選択できることも、重要な視点です」
ポイントは中長期的な視点を持つこと
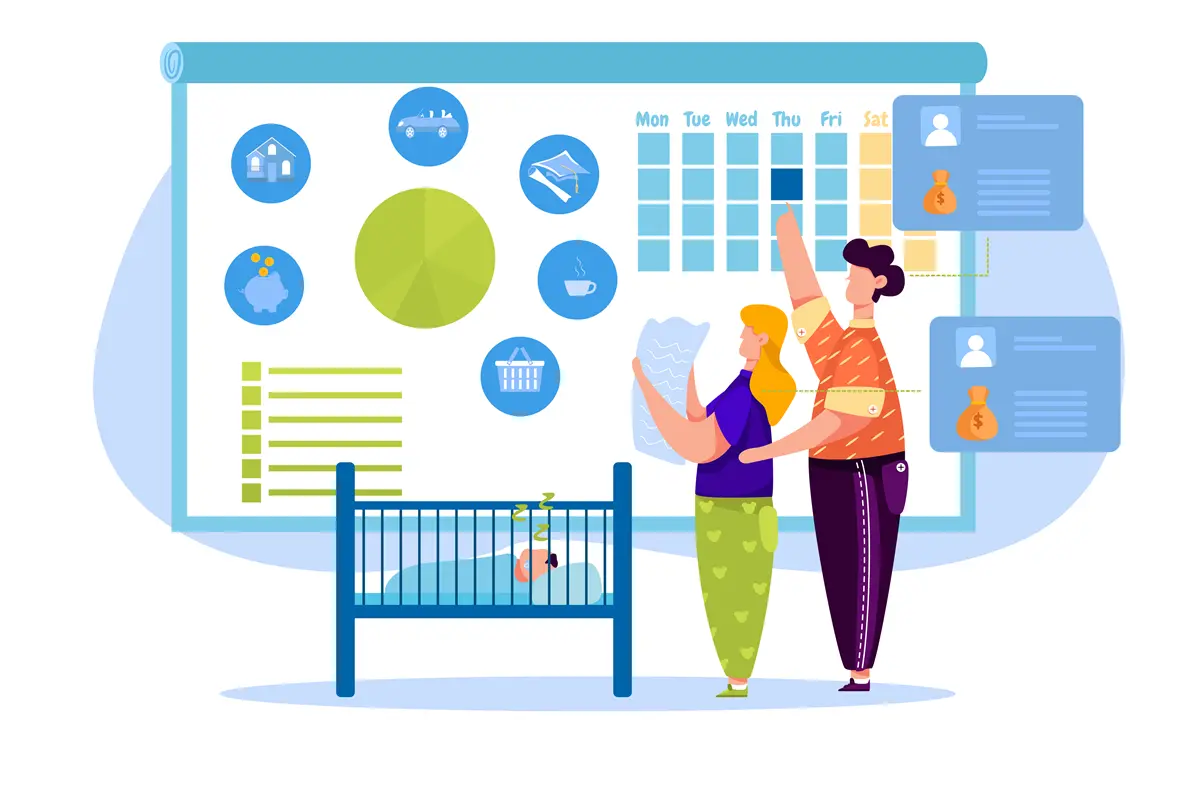
「避妊は、女性・男性のどちらかが責任を持つことではなく、両者がきちんと自分の考えを持ったうえで、話し合って決めるものです。そのためには、女性も避妊について主体性を持つことが大事。決して、女性の責任を増やすものではなく、むしろリスクを減らすことで自己防衛になります。そして、ライフプランを考えたうえでの妊娠・出産のほうが身体的にも、心理的にも負担を減らすことができます。
もしかしたら、男性主体の避妊法であるコンドームに比べると、女性主体の避妊法はちょっと大変と思うかもしれません。ですが、生殖器が外にある男性と、中にある女性では避妊方法が違って当たり前です。それぞれの身体的特徴に適した形で避妊ができるようになっています。
① 予期しない妊娠を防いで健康とキャリアを守ること
② 自己決定権を確保してパートナーの意向に左右されないこと
③ 計画的な妊娠・出産で母体と赤ちゃんの安全を確保すること
中長期的な視点で見てみると、女性主体の避妊の知識と選択肢を持つことはこれらの確保が可能になります。自分で選択する意思を持って、自分に合った方法で安心・安全を守ってくださいね」
執筆/木川誠子
No.00168
2025年5月16日リリース
