ホットフラッシュは閉経前後の7~8割の女性が経験すると言われているほど、更年期の代表的な症状のひとつです。多くの場合は、病気(疾患)ではなく、女性ホルモンの急激な減少の影響を受けて症状が出てきます。ですが、急に熱くなり、汗が出てくると焦ってしまいますよね。また、近年は夏が酷暑なこともあって、「汗なの?ホットフラッシュなの?」と判断が難しいという声も聞かれます。
そこで、漢方医学・自然医学に基づいた診療を行う『イシハラクリニック』副院長の石原新菜先生に、一般的な汗とホットフラッシュの違いとその対処法について教えていただきました。
ホットフラッシュは更年期の代表的な症状
「閉経の前後5年、合計10年を指す更年期は、女性ホルモンが大きく減少し、自律神経のバランスが乱れることで更年期症状が現れます。そのなかでもホットフラッシュは、何の前触れもなく、突然、顔や上半身がカーッと熱くなる、汗が吹き出てくる、動悸がするという症状です。
具体的には、会議中や電車に乗っている時に急に汗が止まらなくなる、就寝中に顔や首が熱くなり、目が覚めてしまう、身体は火照っているのに手足が冷たいなどが見られます」(石原新菜先生・以下同)
一般的な汗とホットフラッシュの違い
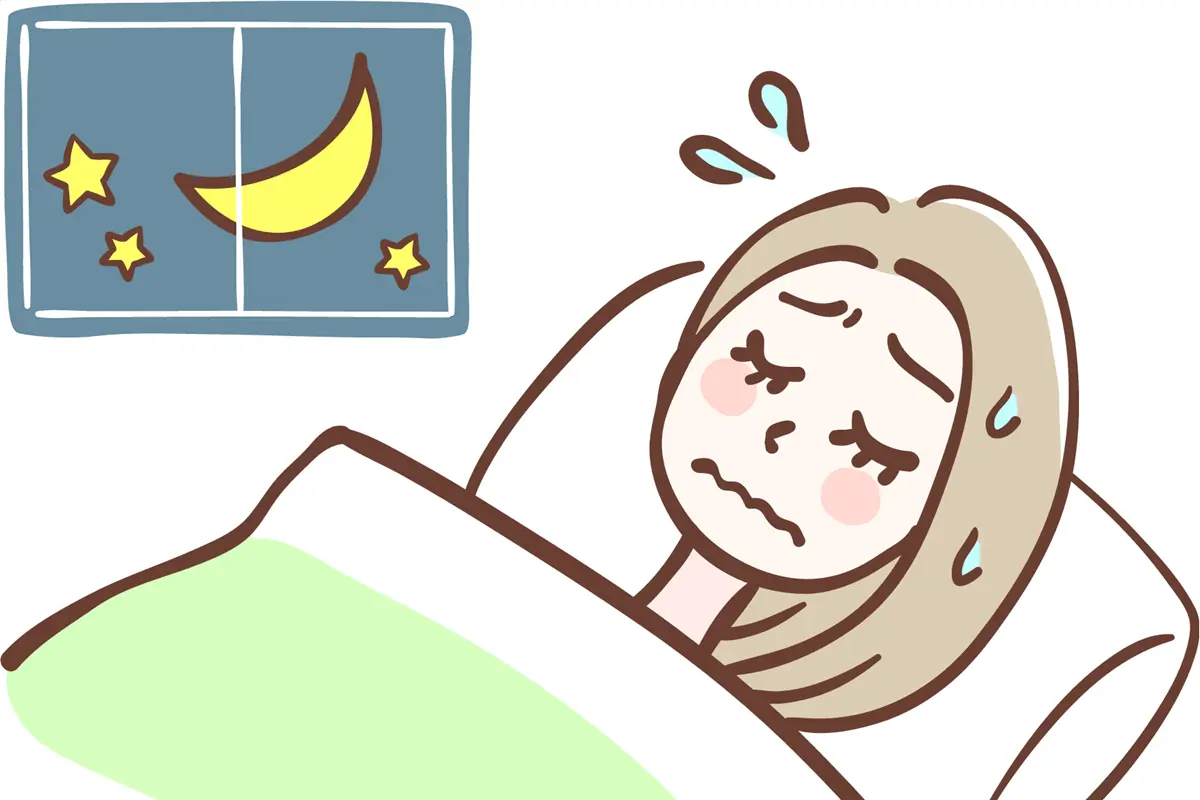
「近年は夏を迎えると35℃を超える日が多く、汗をかきやすい状況です。その場合、汗をかいている理由が明確にわかります。例えば、身体を動かしたから、サウナに入ったから等。そして、全身から汗をかいているというのもポイントになります。
一方、ホットフラッシュは、身体を動かした、動かさないにかかわらず、立ち止まっていても、なぜか突然、汗が噴き出てきます。汗をかく場所も、頭や顔、背中といった上半身の特定の場所からになります。
一般的な汗との大きな違いは、汗をかいている、ほてっているにもかかわらず、自覚できるほど足元は冷えている点です。上熱下寒(じょうねつげかん)といって、いわゆる冷えのぼせ状態にあります。顔がほてっていることもあって、身体が冷えていることに気がつきにくいので注意が必要です」
ホットフラッシュの特徴
□急に汗が出てくる
□頭や背中など、ピンポイントに汗をかく
□なのに足元は冷えていると感じる
一般的な汗の特徴
□気温が高い、運動後などに汗をかく
□全身から汗が出てくる
□冷えている場所はない
ホットフラッシュが起きたその場での対処法

●汗が出ている場所を冷やす
「ホットフラッシュの場合、特定の場所から発汗をしていることが多いです。頭なら頭、背中なら背中というように、汗が出てくる場所を保冷剤や冷たいペットボトル、ハンディファンなどで直接冷やしましょう。また、首やワキなど、太い血管が通る部分を冷やすのも効率的です」
●深呼吸を意識する
「ホットフラッシュが起きている時は、焦る気持ちが出てきやすく、交感神経が優位になりがちです。該当部分を冷やしながら、呼吸も意識しましょう。吸って吐くを繰り返すして気持ちを落ち着かせることも、症状を抑えることにつながります」
ホットフラッシュを抑えるための生活習慣

●足元は温める
「先ほどもお伝えしましたが、ホットフラッシュは冷えのぼせ状態です。足元が冷えていることで上半身に血流が溜まったままでは症状悪化につながります。季節は関係なく、靴下を履く、レッグウォーマーを活用するなど、足元は常に温めましょう」
●温活を意識する
「東洋医学では、冷えは万病のもとと考えられています。ホットフラッシュにも同じことが言えますので、温活は意識した生活習慣を心掛けましょう。腹巻きをする、ショウガ湯を飲む、ひと駅分歩く、湯船につかるなど、日常の中に取り入れやすい温活を心掛けてください」
●規則正しい生活習慣
「栄養バランスを意識した食生活、適度な運動、質のいい睡眠といった、規則正しい生活習慣は健康維持に必要不可欠です。
例えば、カフェインやアルコール、香辛料は、交感神経を刺激して、ホットフラッシュを誘発する可能性があります。香辛料たっぷりのメニューは週1回まで、アルコールは1日1杯までと、無理なく取り組める自分なりのルールで調整しましょう」
●体温調整ができるようにしておく
「ホットフラッシュの症状はいつ現れるのか予測が難しいため、備えておくことも大事です。
出かける際は、通気性や吸湿性がいいコットンやリネンなどの天然素材の洋服を選ぶ、着脱ができる重ね着スタイルを楽しむなど、ファッションでも対策は可能です。
ハンディファンや持ち運びができる冷やしタオルなど、冷やしグッズをバッグにスタンバっておくのも安心につながると思います」
>>>ほてり、のぼせ、発汗……更年期の症状であるホットフラッシュを乗り切る対策アイテム9選
「ホットフラッシュの症状は身体に負担がかかっているサインとも言えるため、抑え込むことや我慢をすることは悪化につながります。精神的な負担も大きくなってしまいますので、日常生活に支障が出るレベルの場合は婦人科を受診して相談してみてください」
執筆/木川誠子
No.00190
2025年10月31日リリース
